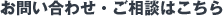【改正】建築物省エネ法について
2020.12.07
こんにちは、井上です。
本日は建築物省エネ法に関してです。
このシリーズは数回に渡ってお届けすることになると思います。
令和3年4月から「建築物省エネ法」が改正されます!
「建築物省エネ法」とは正しくは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」と言い、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的としたものです。(そのままでしたね。)
これらの法律によって、私たちは安全で快適な建築物をお引渡しすることが義務となってたりするわけです。
冒頭にも申し上げましたが、令和3年4月の改正によって「建築物省エネ法」はより強力なものとなります。
具体的なポイントは以下の4つ。
①(省エネ基準)適合義務制度の対象拡大
②(省エネ基準)説明義務制度の創立
③住宅トップランナー制度の対象拡大
④地域区分の見直し
では一つずつ追っていきましょう。
①(省エネ基準)適合義務制度の対象拡大
この辺りは住宅に関して関係性がないのでサラッと。
300㎡以上2000㎡未満の非住宅建築物は届出義務から適合義務に代わります。
これによって、以前は着工日の21日前に省エネ計画の提出で済んでいたものが、4月からは適合性判定を受ける必要性があります。
②(省エネ基準)説明義務制度の創立
こちらは300㎡未満の小規模建築物や住宅が対象の内容ですね。
改正以前は努力義務であり強制力もなかったのですが、本改正より説明義務が加えられました。
これによって実物件の外皮性能(簡単にいえばどれだけ熱の流出を防げるかという住宅の性能を指します。)を計算し、その結果を書面でもって建築主に開示・説明する必要があります。
これで悪いことができなくなっちゃったんですね。
もちろんしませんが!
省エネ基準への適否はもちろん、もし基準に満たない場合は対策措置までが説明義務となっています。
もちろんお客様は性能の高い住宅をお求めですし、性能の低い住宅なんてごめんですよね。
結果としては努力義務よりも、事実上はほぼ適合義務に近い形での施行となりますね。
③住宅トップランナー制度の対象拡大
こちらはあまり関係ないですが、以前は建売戸建(150棟/年以上)を行うメーカーが対象であったのが、注文戸建、賃貸アパートなども対象に含まれることとなりました。
トップランナーの省エネ率は基準値よりも10~20%ほどの削減が必要となっております。
なので住宅トップランナーを掲げるメーカーというのはいより性能が高いのだ、と安易に考えることも可能です。
④地域区分の見直し
省エネ基準値は地域に応じて設定されています。(1~8段階)
気候の変化にしたがってアップグレードされていくため、都度地域に見合った性能が法的に求められるわけですね。
いかがでしたか?
こういう事情も知っておくと、住宅を購入する際の安心材料にもなるのではないでしょうか?
日本の住宅性能の底上げが期待されるため、より安全で安心、そしてエネルギーロスの少ない住宅が増えることによって環境への影響も考えられます。
私たちの仕事は増えますが…orz
いや、頑張りますよ!
滋賀で土地探し・注文住宅を建てるならエールコーポレーションまで!